ウィンストン・チャーチル、ザ・ビートルズを別にすれば、世界で最も有名なイギリス人は、少なくとも犯罪の分野では切り裂きジャックを措いて他にない。
──ハロルド・シェクター Harold Schecter & デヴィッド・エヴェリット David Everitt 共著 A to Z Encyclopedia of Serial Killers by (1996)より。
文句や反論はおれではなく、著者たちに直接言って頂きたい。
今さら説明の要もないとは思うが、おさらいの意味で確認しておこう。切り裂きジャックは1888年8月から11月にかけてロンドンで跳梁したシリアルキラー。被害者5人はすべて街娼で、犯行はロンドンのホワイトチャペルと呼ばれる一角で行われている。頭のおかしい医師から売春婦に怨みを持つ女性まで、その正体を巡ってさまざまな仮説・憶測が飛び交ったが、結局犯人確定につながる証拠・情報は何ひとつ得られず、真相は謎のままに終った。動機は不明だが、快楽殺人の可能性があることから「近代犯罪史におけるセックス殺人の第一号」と見なされている。だが実際は1861年〜1866年にパリで性的快楽のため8 人の売春婦と1人の少女を殺したジョセフ・フィリペの先例がある。ジャックが初めての事例ではないのである。
また被害者数や手口の残忍さからいっても、1970年代〜80年代にエクアドル、コロンビア、ペルーの3ヶ国を渡り歩きながら300人以上の幼女・少女を殺害したペドロ・アロンソ・ロペスのように、切り裂きジャックを上回る凶悪犯の存在は、犯罪史上、決して珍しくはない。にもかかわらず切り裂きジャックが彼ら以上の人気を、しかも足かけ3世紀にもわたって保ち続けている理由は、彼がマスコミを通じて犯行を誇示する「劇場型犯罪」の元祖だったこと、最後まで正体が明らかにならなかったこと、舞台がヴィクトリア朝末ロンドンという文化史的にみて興味深い時代・場所であったこと──などがあげられる。歴史ミステリ的な興味を喚起しやすいのである。実際、ジャックの正体や、犯行と時代背景との関わりを考察するリパロロジー(切り裂きジャック学)なる分野が存在する。
日本人によって書かれた戦前の切り裂きジャック文献のうち、最も有名なものは、牧逸馬の「女肉を料理する男」だろう。牧逸馬は明治33(1900)年、佐渡島の生まれ。本名長谷川海太郎。18歳で渡米し、コックやスクールボーイなどをしながら大学に通う。大正13(1924)年に帰国。谷譲次、林不忘、牧逸馬の3つのペンネームを使って文筆活動を開始する。1人の作家が複数のペンネームを使うのは別に珍しいことではないが、牧のように、谷譲次の名でアメリカにおける日本人の生活をユーモラスに描いた「めりけん・じゃっぷ」ものを、林不忘の名で丹下左膳シリーズに代表される時代小説を、牧逸馬の名で現代小説や翻訳を──といった具合に、まるでペンネームひとつひとつが独立した人格であるかのごとく、異なる分野で活躍した例はあまり聞かない。昭和10 (1935)年急逝。
「女肉を料理する男」は「世界怪奇実話」シリーズの第1話として、「中央公論」の昭和4(1929)年10、11月号に分載された。同シリーズは世界各地(といっても欧米圏に限られるが)の「怪奇な事実物語」(牧逸馬)を題材としたノンフィクションで、桃源社版「世界怪奇実話」第1巻(1969)に付された尾崎秀樹の解説によれば「新聞や雑誌、あるいは単行本などをひろく蒐集すると同時に、時には実際に事件の現場をたずね、関係者にも会って事件の客観的な調査にあた」るなど、入念なリサーチを経て執筆されたという。テーマはタイタニック号沈没やマタ・ハリの秘話といったメロドラマチックな話題から、反進化論裁判のような珍談レベルのユーモラスな事件まで、多岐にわたっている。だが「世界怪奇実話」の最もユニークな点は、保険金目当てに3人の女性を浴槽で溺死させたジョージ・ジョセフ・スミス、結婚話に釣られて自宅を訪れた独身男を斧で惨殺しては拐帯金を奪い取ったベル・ガネスのようなシリアルキラーの事例を積極的に取りあげたことにある。シリアルキラーという言葉すらない時代、連続殺人に着目した牧の直感力の鋭さ、先見性の高さにはおどろかされる。同時代の松本泰、伊東鋭太郎らの犯罪実話が忘れ去られたにもかかわらず、「世界怪奇実話」がくり返し復刊(桃源社1969、社会思想社1975、山手書房新社 1993、光文社2003、文元社2004)される理由も、この辺にあるのではないだろうか。
ところで「女肉を料理する男」には、興味深い逸話が含まれている。「マシュウ・パッカア」なる男が経営する果物屋に、男が立ち寄り、黒葡萄を一袋買い求めた。女はエリザベス・ストライドという名の街娼で、彼女はその1時間30分後、死体となって発見された。切り裂きジャックによる3回目の犯行である。死体の周囲には、紙袋と葡萄の皮が散乱していた。この「黒葡萄を買った男」こそ切り裂きジャックだったのではないか? というのだ。もし事実ならば大変なことだ。何しろジャックを間近で目撃したばかりか、会話まで交わしたというのだから。
「牧逸馬の世界怪奇実話」(2003)の解説で、島田荘司氏は「この作には衝撃的な重大記述があり、現在読めるあらゆる切り裂きジャック関連の資料を渉猟しても、この記載はここにしか見えない。これが事実なら、この有名事件は180度様相が変化する可能性もあり、これが牧氏一流のフィクションか、それとも牧氏だけが手にできた貴重な資料によるものなのかを、もっか大いに悩まされている」と述べておられる。たしかにドナルド・ランベロー「十人の切り裂きジャック」(1975、邦訳は草思社)やコリン・ウィルソン&ロビン・オーデル共著「切り裂きジャック 世紀末ロンドンの殺人鬼は誰だったのか?」(1987、邦訳は徳間書店)など、基本的なリッパー研究書の中には、パッカアのパの字もない。
創作か、実話か。後者だとすると、情報の出所はどこか。名だたるリパロロジスト(切り裂きジャック研究家)もその存在を知らない、ウルトラレアなネタ本があって、牧はそれを所持していたのではないか? 残念ながら牧の蔵書リストは公開されておらず、参考文献を直接知るすべはない。ならば間接的なヒントが文中に隠れてはいないか。とりあえず「女肉を料理する男」の本文から、事件当事者以外の人名を洗い出してみた。引っかかったのは「精神病理学者として令名あるフォウブス・ウィンスロウ博士」と「新聞記者ガイ・ロウガン氏」の二人。次にロス・ストラカン Ross Strachan というイギリスの切り裂きジャック蒐集家が編集した世界の切り裂きジャック文献&グッズの総カタログ The Jack theRipper Handbook(1999)で「フォウブス・ウィンスロウ」「ガイ・ロウガン」を調べると、次のような本に行き当たる。
Recollections of Forty Years by L. Forbes Winslow(1910)
Masters of Crime by Guy B. H. Logan(1928)
早速、ウィンスロウの著書に目を通してみた。結果はスカ。パッカアに関する記述は一行もなかった。その代わりちょっと面白いことが分かった。小酒井不木のエッセイ「殺人探偵」(1923)に
世界的に有名な犯罪学者ウインスロウ氏も、毎夜探検に出た一人であつたがあるとき新聞に『ロンドン市の醜業婦撲滅を期する紳士あり、同意の士を求む。』と広告すると、無名の男から数回手紙が来て、自分は醜業婦撲滅を期するため、直接手段に出づるのであると述べ、次回の殺人を十一月九日に行ふと通信した。すると果して、その日にケリーなる私娼が白昼、いつもと同じやうに惨殺されたのでウインスロウ氏はこの通信者が犯人に違ひないとは思つたがとんと探索する手段がなかつた。兎角する中遂にある日、『ジヤツク・ゼ・リツパーはもう殺人は行ひません。』といふ文句を書いた紙が氏の門の傍に置かれてあつて、さしも人を騒がせた殺人も、その後パタリ止んでしまつたのである。
とあるのだが、この「犯罪学者ウインスロウ氏」が Recollections of FortyYears の著者フォーブス・ウィンスロウだったのである。不木が参照したのと同じ本を、いま自分が読んでいるかと思うと、ちょっとうれしい。ついでながら「切り裂きジャックは二度と殺人を犯さない」と書いてあったのは街路の壁である。あの不木でさえ曖昧な記憶を元に原稿を執筆したりするのかと、妙に感心したものであった。なお原書にはジャックからウィンスロウ宛の手紙が図版として掲げられており、それにはあたかも英語の授業で筆記体を覚えたばかりの日本の中学生が書いたような、きわめて判読しやすい筆跡で「ジャック・ザ・リパー」とサインが入っている。真面目過ぎる人だったようであるウィンスロウ博士という御仁は。
残るは Masters of Murder である。この本は、L・C・ダウスウェイト L.C.Douthwaite の Mass Murder(1928)と共に、連続殺人だけを扱った犯罪実話集としては世界最初期の刊行物である。当時はまだシリアルマーダー(連続殺人)という用語は存在せず、ローガンはマルチプルマーダー(複合殺人)またはホールセールマーダー(大規模殺人)、ダウスウェイトはマスマーダー(大量殺人)という言葉を使っている。一時期猟奇殺人が起こるたびに日本のテレビ局からコメントを求められ、適当、いや適切な見解を披露していた元FBI特別捜査官ロバート・K・レスラーは、トム・シャットマンとの共著「FBI心理分析官」(1992、邦訳は早川書房)の中で、連続殺人という言葉は自分が使い始めた──と主張している。だがマイケル・ニュートンの「シリアルキラー百科」(2000)によると、1966年にイギリスで出版されたある本の中で、すでにシリアルマーダラー(連続殺人犯)という言葉が使われており、しかもレスラーは1974年に訪英しているという。大事なことなので、もう一回、言おう。訪英しているという。名称が何であれ「経済的または性的欲求を満たすために一定の感覚を置いて殺人をくり返すタイプの犯罪者あるいはその犯罪」という概念が1920年代末に確立していたことは確かである。
閑話休題。ローガンの本をひもといてみた。果たせるかな、パッカアの話が出てくる。該当箇所を抜粋訳してみよう。
当時──あるいは今でもそこにあるかも知れない──バーナー街の44番地に、一軒の小さな果物屋があった。主人はマシュー・パッカーといい、狭い店内に客が足を踏み入れる煩雑さを解消するために、窓から応対するようになっていた。1888年9月30日〔会津注・正しくは9月29日〕土曜日の午後11時30 分、見知った女が、男と一緒にやってきた。エリザベス・ストライド──通称「のっぽのリズ」──は近所でも札付きの女だったので、パッカーもよく知っていたのである。男の方は誰だか分からなかったが、2、3度見かけたことがあり、顔に見覚えがあった。
その男は店の窓口に立ち止まると、安物の黒葡萄を指さし、いくぶん荒っぽい口調で半ポンド言いつけ、代価として3ペニー支払った。彼はつとめて暗がりに身を潜めようとする様子で、パッカーの視線を感じると顔を背けた。だがパッカーの目には、男の風体がはっきりと焼きついていた。それは30がらみで、背丈は5フィート7インチほど。がっちりした体型の、肌の浅黒い、きれいにヒゲを剃った、抜け目ない感じの男だった。黒い膝丈のオバーコートにフエルトのソフト帽をかぶり、口調は早口で、キビキビしていた。
一方、牧逸馬の「女肉を料理する男」はこうだ。
当時──いまでもあるが──バアナア街四四番地に、ささやかな果物屋があった。マシュウ・パッカアという男が細君相手に小さく経営している。狭い土間に果物が山のように積んであるので、店へ客がはいってくると邪魔になる。売る方も買うほうも身動きが取れなくなってしまう。そこで一策を案出して、表の戸を締めきり、それに小窓を開けて、ちょうど停車場か劇場の切符売場のような特別の設備をし、自分は内部におさまって、この窓から外を覗いている。客には窓をつうじて応対し、品物も窓から出してやろうという一風変わった人物だ。
九月三十日、土曜日の午後十一時半ごろだった。
このパッカアが、もうそろそろ店を閉めようとして支度しているところへ、窓のむこうに男女人伴れの客が立った。男は、見たことがなかったが、女はパッカアもよく知っていた。のっぽのリッツ──エリザベス・ストライド──で、この付近で名うての不良少女だった。
パッカアは妙にこのリッツの同伴者が気になったとみえて、それとも人物それ自身が印象的な風貌を備えていたのか、じつに詳しくその人相服装を覚えて、後日逐一申し立てている。
年齢三十歳前後、身長約五フィート七インチ、肩幅広く、身体全体が四角い感じを与える。浅黒い皮膚。綺麗に鬚を剃って、敏捷な顔つきをしていた。長い黒の外套に、焦茶色フェルト帽、きびきびした早口だった。/そのきびきびした横柄な早口で、エリザベスの同伴者は、窓のむこうから言った。/「おい。そこの葡萄を半ポンドくれ。三ペンスだな。」
物価の安かったころである。
似ている。ネタ(情報)の並べ順だけでなく、挿入句の位置・内容まで同じだ。偶然とは思えない。おまけにローガンの書き誤りが、そのまま踏襲されている。ストライドが殺害されたのは9月30日の日曜日。土曜は29日なのである。ちなみに彼女が「不良少女」というのはまちがい。実際は死亡時44歳のおばさんだった。「狭い土間に果物が山のように積んで」云々は創作だろう。痛みやすいフルーツを土間に積み重ねるはずがない。牧が「大犯罪者」を参照していることは確実だ。ではなぜリパロロジストたちはパッカーを無視するのか。捜査記録に照らし合わせると、パッカーの証言には、おかしな点があることに気がつく。
(1)容疑者の風貌に関する疑問。パッカーによれば、ストライドが「きれいにヒゲを剃った男」と彼の店を訪れたのは、9月29日の午後11時30分だという。ところが彼女は1時間5分後(9月30日午前12時35分)に「小さな黒い口髭」の男と、さらに1時間15分後(同日午前12時45分)には「小さな褐色の口髭」の男と連れ立って歩いているところを、それぞれ別の人物に目撃されている。
(2)検視結果との矛盾。ストライドの遺体を検視したジョージ・バグスター・フィリップス医師は「死亡する何時間かのあいだに、故人は葡萄の皮や果肉を飲み込んでいない」と証言し、また「胃の内容物は半ば消化されていたが、チーズ、じゃがいも、穀粉」(「十人の切り裂きジャック」)と報告している。
パッカーの証言は作り話である可能性が高く、事実だとしても証拠としての価値はない。だからリパロロジストたちは無視した。これが答えだ。ガセネタをパクるとは「新聞や雑誌、あるいは単行本などをひろく蒐集すると同時に、時には実際に事件の現場をたずね、関係者にも会って事件の客観的な調査にあた」った牧らしからぬ、アイタタな失態である。牧が複数の資料を組み合わせ、情報の取捨選択を行いながら、事件を多角的に描いたという従来の説には疑問がある。全体にわたり検証したわけではないので、断定的なことは言えないが、少なくともいくつかのエピソードは1、2冊のネタ本を元に書かれたものであることが分かっている。判明する範囲で「世界怪奇実話」の元ネタをあげておこう。
「都会の類人猿」 → Mass Murder by L. C. Douthwaite(1928)
「肉屋に化けた人鬼」 → Mass Murder by L. C. Douthwaite(1928)
「生きている戦死者」 → Bela Kiss by William Le Queux(年度不明)
「女肉を料理する男」 → Masters of Crime by Guy B. H. Logan(1928)
「ロウモン街の自殺ホテル」 → Warped in the Making: Crimes of Love and
Hate by H. Ashton-Wolfe(1927)
発行年度にご注意願いたい。「浴槽の花嫁」(1975)の解説で、松本清張は「さて、ロンドンについた牧夫妻は早速、古本屋漁りをはじめた。もともと牧はロンドンが好きだったが、彼が降っても照っても毎日通う本屋が一軒あった。(中略)牧はそこで、殺人事件とか、行方不明人とか、牢破りとかいった本、しかも高価な本をどんどん買った」と述べいる。牧が中央公論社特派員としてロンドンを訪れたのは昭和3(1928)年。古本屋に通い詰めるまでもなく Mass Murder、Masters of Crime、Warped in the Making は新刊書店の店頭で容易に手に入ったのである。
ネタの調理方法にも問題がある。「生きている戦死者」は Bela Kiss のかなり忠実な翻訳で、原文を自己流の文章にリライトした「焼き直し」ですらない。「自殺室」は事件の主犯であるベトナム人ハノイ・シャンがフー・マンチュー博士のモデルではないか──との指摘がSF作家フィリップ・ホセ・ファーマーによってなされ、海外の研究家が検証を行ったものの、ハノイ・シャンの実在を裏付ける資料はアシュトン=ウルフの著書以外に発見できず、そのため創作説さえ囁かれている。そもそもベトナム人の氏名は「姓・ミドルネーム・名」の順なので、アシュトン=ウルフがハノイ・シャンを「シャン」と呼ぶのは、チャーチルをウィンストンと呼ぶようなものなのだ。子供の頃、秋田書店の「世界の怪奇スリラー全集」の1冊(真樹日佐夫の「世界の謎と恐怖」だったか?)でこの自殺ホテルのエピソードを読み、異様な感銘に打たれた経験のあるおれとしては、正直、失望せざるを得ない。ようするに事実であるかどうかという、根本的な部分での確認作業すら、牧は行っていなかったのである。
誤解のないように言っておくが、別におれはここで「世界怪奇実話」を貶めようと思っているわけではない。実話読物としては文句なしに面白い。そのことは、ローガンの文章と「女肉を料理する男」を読みくらべてみればよく分かる。牧の文章には「実際に現場を見てきた人」から直接話を聞いているような、生々しい臨場感が漂っている。店の説明により多くの字数を費やし、「今でもそこにあるかも知れない」を「いまでもあるが」に言い換えただけで、これだけの差が生じるのだ。天性の才能としか言いようがない。だが、それはそれ、これはこれ。そろそろ「膨大な英文資料」(島田荘司氏)を元に「世界怪奇実話」が書かれたという「牧逸馬伝説」から解放されるべきではないか。「世界怪奇実話」の正しい評価は、そこから始まるように思われるのである。
2010年2月
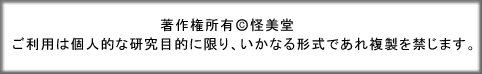
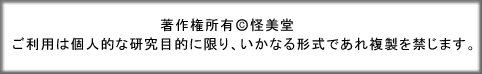
![]()
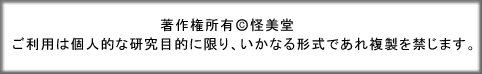
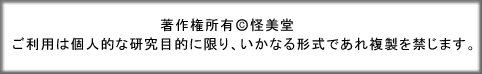
![]()