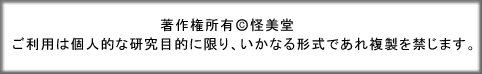
(1)
会津信吾
「ある青年」の死
|
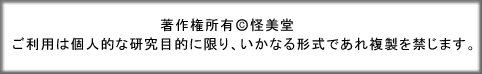
「ある青年」の死
|
「祖国を出でゝ祖国へ」の執筆
転向の原因を知る手がかりは、もう一つある。
ところがこれと酷似した漫画を実際に中国で見たことを、平田は『軍縮の不安と太平洋戦争』の中で書いている。平田は大正10年10月ごろ、上海に滞在していたことがあった。党務、おそらくはコミンテルンとの連絡が目的と思われ、翌月長崎入港と同時に不穏ビラ事件で逮捕されてしまう。次の文章は、その際に体験した出来事だろう。
これが転向の決定的な原因だ、と断じるわけではない。だが平田の内なる「民族」が、平田をして社会主義を捨てさしめ、軍事研究へと走らせたのではないか。そう考えることで、正反対の道を選んだ理由の一端が理解できるのではないか。 |
軍事ジャーナリストとしての出発
「祖国を出でゝ祖国へ」で転向宣言(?)した平田は、ひきつづき「日本及日本人」に政治・国際評論を発表し、ジャーナリズムの中に根をおろしていく。タイトルを列記してみると、
ご覧のように、昭和3、4年の平田はまだ日米関係を射程に入れていない。平田がアメリカを仮想敵とみなすのは、ロンドン会議以降のことである。昭和5年1月、英首相J・R・マクドナルドの提唱で英・米・日・仏・伊の五ヶ国が参加したこの会議では、英・米・日の補助艦保有数の比率が10
:10 :7と決定された。これを不満とする海軍軍令部が政府を攻撃し、いわゆる「統帥権干犯問題」にまで発展した。
福永恭助が感心したのは、ひとつには平田が軍外部の民間人だったということもあるだろう。当時の軍事ジャーナリスト・軍事小説家には、軍出身者が圧倒的に多かった。たとえば海軍に限ってみても匝瑳胤次(少将)、水野広徳(大佐)、広瀬彦太(同)、小沢覚輔(同)、中島武(少佐)、川田功(同)らがいる。 |
Copyright © 怪美堂 All Rights Reserved.